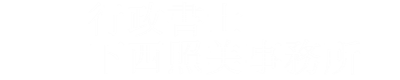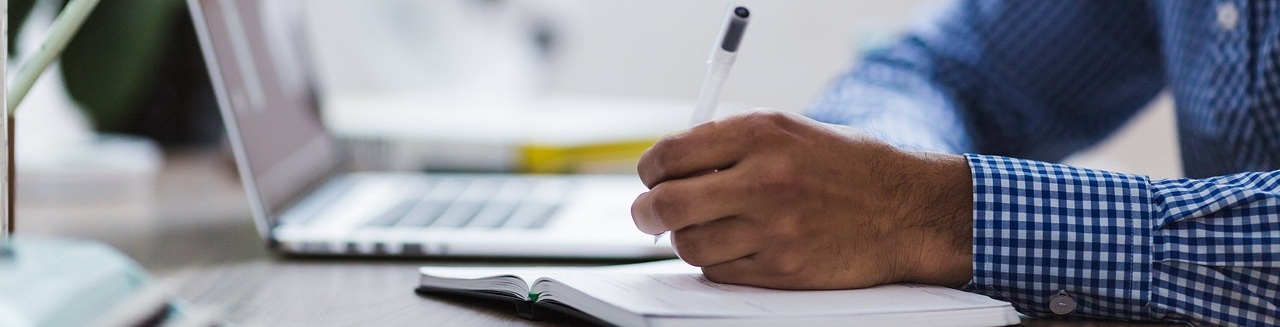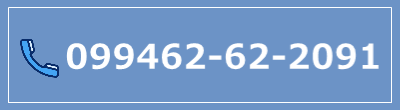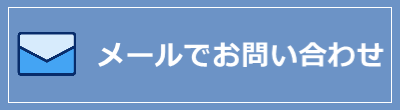遺言書とは
遺言は、大切なご家族への想いを形に残す、人生最後の大切な意思表示です。
しかし、書き方や内容に不備があると無効になったり、かえってトラブルの原因になることもあります。
遺された家族が迷わず、安心して手続きを進められるよう、法的に有効な遺言を準備することが大切です。
ここでは、終活で注目される理由や目的、種類など、遺言書についてご説明します。
①遺言書が注目される時代背景
近年、「終活」の一環として遺言書を作成する人が増えています。
少子高齢化や核家族化の進行により、家族間の関係性が複雑化する中、「自分の意思を明確に残しておきたい」という思いが高まっているからです。
実際、相続をめぐる家族間のトラブル(いわゆる争族)は年々増加傾向にあり、遺言書はその防止策として有効な手段となっています。
②遺言書の目的とは
遺言の目的は、単に財産の分け方を決めるだけにとどまりません。
以下のように、様々な意味と効果を持っています。
【遺言書の主な目的】
- 相続人同士の争いを未然に防ぐ
- 法定相続分とは異なる意思を反映できる
- 特定の人に財産を残すことができる(例えば、内縁の配偶者や世話になった人)
- 相続人以外の者への遺贈が可能になる
- 子の認知や、未成年後見人の指定なども可能
こうした目的を実現するには、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。無効な遺言書では、かえってトラブルの原因になりかねません。
そのため、自分の状況や意図に合った適切な方式を選ぶ必要があります。
③遺言の種類とそれぞれの特徴
遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や注意点があります。以下の表に主な3つの方式をまとめました。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書き、日付と署名押印が必要 | 手軽に作成できる。費用がほとんどかからない | 書き間違いによる無効リスク。家庭裁判所での検認が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成し、公証役場で保管される | 法的に確実。検認不要ですぐに手続きが進められる | 費用がかかる。証人2人の立会いが必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできるが、公証役場で手続きが必要 | 内容を誰にも知られずに済む | 様式不備で無効となるリスクが高い。家庭裁判所の検認が必要 |
このように、それぞれの方式にはメリットとデメリットがあります。
最も利用されているのは「公正証書遺言」で、確実性が高く、紛失や偽造のリスクが低いため安心です。
一方で、費用や手続きがやや煩雑なため、時間やコストをかけられない方は「自筆証書遺言」を選ぶケースもあります。
④法務局による自筆証書遺言の保管制度
なお、2020年7月からは「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が始まり、自筆証書遺言を法務局に預けることで紛失や偽造の心配がなくなり、検認も不要になりました。
これにより、自筆証書遺言の利用が一層しやすくなっています。
【法務局保管制度の概要】
- 保管申請は本人が法務局に出向いて行う(代理不可)
- 本人確認や内容の確認が行われる
- 保管された遺言書は家庭裁判所の検認不要
- 相続人は、法務局で遺言書の有無を確認できる
この制度により、「手軽に作成したいが、法的に有効で安全に保管したい」というニーズに応えられるようになりました。
⑤遺言書は定期的な見直しが大切
また、遺言は一度作成すれば終わりではありません。
ライフステージや財産状況の変化に応じて、定期的に見直し・変更することが大切です。
最新の意思が反映されるよう、複数回書くことも可能です(最新の日付の遺言が有効になります)。
⑥専門家のサポートで安心な遺言書作成を
最後に、遺言書を作成する際には、法的要件を満たしていなければ無効になるおそれがあるため、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
当事務所では、遺言のご相談から作成サポート、公証人との連携まで一貫して対応しております。
将来の不安を減らし、安心して人生を過ごすために。ご自身の想いを、法的に有効なかたちで残してみませんか。