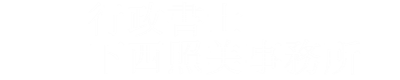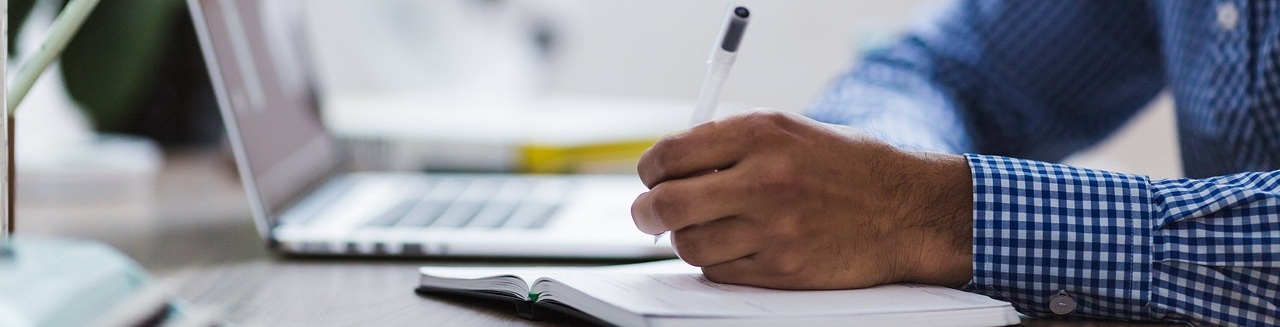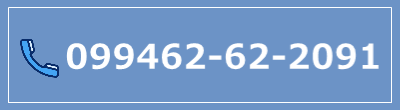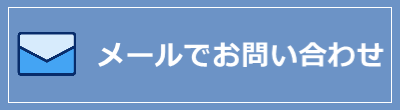相続手続きの流れ
ご家族を亡くされた悲しみの中、相続手続きを進めるのは大きな負担です。
しかし、相続放棄には3か月以内の期限があり、戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議など、やるべきことは多岐にわたります。
手続きの遅れや誤りは、思わぬトラブルにつながることもあります。
不安な状況の中でも落ち着いて進められるよう、相続手続きの流れを8項目についてご説明します。
① 死亡届の提出
人が亡くなると、まず市区町村役場へ「死亡届」を提出する必要があります。これは法律上、死亡の事実を7日以内に届け出る義務があるからです。
通常、医師が発行する死亡診断書と一体の様式になっており、葬儀社が代行することもあります。
死亡届の提出によって火葬許可証が交付され、葬儀や火葬が行えるようになります。
この届出が済んでいないと、相続を含むさまざまな行政手続きに進めないため、最初に行うべき重要な工程です。
② 遺言書の有無の確認
故人が遺言書を残していた場合、それが相続の内容や手続きに大きく影響します。
自筆の遺言書を発見した場合、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です(公正証書遺言は検認不要)。
遺言書が有効であれば、その内容に従って財産を分けるため、相続人全員による遺産分割協議が不要になる場合もあります。
逆に、遺言書がなければ法定相続人全員による協議が必要です。早い段階で遺言書の有無を確認することが、その後の流れを決める鍵になります。
③ 相続人の確定
相続手続きでは、誰が相続人なのかを正確に特定する必要があります。
これは、戸籍謄本をもとに、故人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得して行います。
離婚歴や認知した子がいるなど、家庭関係が複雑な場合、思わぬ相続人が現れることもあります。
相続人の一人でも抜け落ちると、遺産分割協議が無効になるおそれがあるため、正確かつ慎重な調査が必要です。
この作業は煩雑で時間がかかるため、行政書士に依頼される方も多い工程です。
④ 相続財産の調査
相続財産には、プラスの財産(不動産・預貯金・株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローンなど)も含まれます。
故人がどんな財産を持っていたかを調査し、全体像を把握することが重要です。
通帳、不動産の登記簿謄本、保険証券、借用書などを確認し、財産目録を作成します。
この時点で負債が多いことが判明すれば、相続放棄や限定承認を検討する判断材料にもなります。
見落としがあると後にトラブルになるため、丁寧な調査が不可欠です。
⑤ 相続放棄・限定承認の検討
調査の結果、相続財産よりも負債が多いと分かった場合、相続を放棄することも可能です。
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
財産と負債のバランスが不明なときは、限定承認という制度を選ぶこともできます。
これも同じく3ヶ月以内の申述が必要です。判断を誤ると、知らぬ間に借金も相続してしまうことがあるため、早期の調査と正しい手続きが求められます。
⑥ 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、どの財産を誰が相続するかを決める必要があります。
これを「遺産分割協議」といい、相続人全員の同意が必要です。一部でも合意できない場合、協議は成立しません。
現金や不動産、株などの配分はもちろん、「誰が何を引き継ぐべきか」といった感情面でも争いになりがちです。
トラブルを防ぐためにも、法的知識に基づいて冷静に話し合いを進めることが重要です。
行政書士が中立的に支援することで、協議がスムーズに進むケースが多くあります。
⑦ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、その内容を書面にまとめる必要があります。
これが「遺産分割協議書」です。この書類がないと、預貯金の払戻しや不動産の名義変更など、各種の相続手続きが進められません。
協議書には、全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要であり、不備があると金融機関や法務局で受け付けてもらえません。
行政書士が作成すれば、形式や法的要件を満たした確実な文書を準備でき、安心して提出できます。
⑧ 各種名義変更手続き
遺産分割協議書に基づいて、相続財産ごとの名義変更手続きを行います。
不動産は法務局で所有権移転登記、預貯金は各金融機関での手続き、自動車は運輸支局への申請が必要です。
それぞれ提出先や書類の内容が異なるため、相続人が自分で行うには手間がかかります。また、手続きの順序にも注意が必要です。
たとえば、不動産の登記変更には遺産分割協議書の原本が必要であるなど、書類管理にも細心の注意が求められます。
行政書士が書類作成や手続きを代行することで、手続きの漏れやミスを防げます。