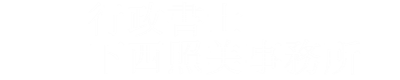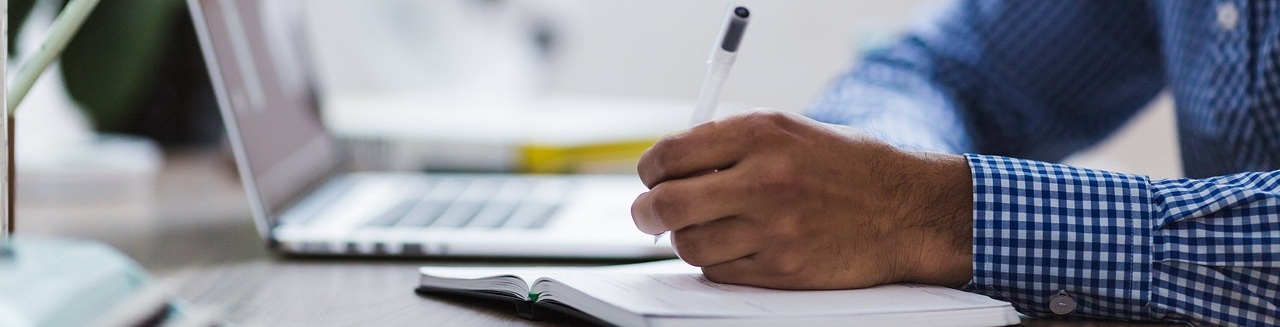任意後見とは
~「もしも」の備え、できていますか?~
高齢化が進む現代、「判断力が低下したときの備え」は誰にとっても重要なテーマです。
けれども、多くの方が「自分はまだ元気だから」「うちには子どもがいないけど何とかなるだろう」と、つい先送りにしてしまいます。
しかし、いざという時に「誰に任せるか」「どうしてほしいか」を事前に決めておくことは、自分自身の尊厳を守るとともに、家族や周囲の人の負担を軽くする大切な準備です。
任意後見制度は、そんな“まだ元気なうちに考えておくべき大事なこと”のひとつです。
この記事では、制度のしくみや手続きの流れ、法定後見制度との違い、そして行政書士にできるサポート内容まで、わかりやすくご紹介します。
あなたにも関係があるかもしれません
こんなお悩み・心配ごとはありませんか?
- 将来認知症になったとき、自分のお金の管理は誰に任せるのか不安
- 子どもがいない夫婦で、どちらかにもしものことがあったら心配
- 身近に頼れる親族がいないが、身の回りのことを誰かに見守ってほしい
- できるだけ迷惑をかけず、老後を自分らしく過ごしたい
これらは決して特別なケースではありません。実際に、相談を受ける方の多くが「自分たちにも必要かも」と感じたことをきっかけに動き出されています。
「まだ早いかも」と思っている今こそ、考えるタイミングです。
任意後見制度とは?
◎制度の概要
任意後見制度とは、「判断能力があるうちに、自分が信頼できる人(任意後見人)をあらかじめ契約で決めておく制度」です。
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、財産管理や生活支援について、自分の希望に沿った内容をあらかじめ契約で定めておきます。
◎利用の流れ
1.契約の準備
任意後見人候補者と支援内容について合意し、公正証書で「任意後見契約」を締結します。
2.判断能力が低下
認知症などで本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に申し立てを行います。
3.任意後見監督人が選任される
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が発効します。
4.後見人による支援開始
任意後見人が、財産管理や生活支援などの後見業務を開始します。
法定後見制度との違い
「任意後見」と「法定後見」の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が不十分になった後に申立て |
| 後見人の選任者 | 本人が自由に選べる | 家庭裁判所が選任 |
| 後見内容の決定方法 | 本人の希望に沿って自由に契約できる | 家庭裁判所が決定 |
| 契約方法 | 公正証書で任意後見契約を結ぶ | 家庭裁判所に申立てが必要 |
| 柔軟性 | 高い(見守り・死後事務契約とセットにできる) | 低め |
よくあるご相談
はい、信頼できる第三者(知人、行政書士など)でも契約は可能です。
本人に判断能力がある間であれば、契約の内容変更・解除は可能です。
公正証書作成の費用や、行政書士への報酬などがかかりますが、内容によって異なりますので事前にご案内いたします。
まずは一歩、未来の安心のために
任意後見制度は、将来の「もしも」に備える心強い制度です。
でもその一歩が、不安だったり、難しそうに思えたりする方も少なくありません。
当事務所では、専門用語を使わず、ゆっくり丁寧にご説明し、無理のないペースでご準備を進めていただけるよう心がけています。
「自分のことを信頼できる誰かに託しておきたい」
「子どもがいないので、老後の備えを考えておきたい」
そんなお悩みがある方は、まずはお気軽にお尋ねください。